|
「みんなの環境」第22号では、
直近3年間の二酸化窒素(NO2)
濃度の測定結果を報告しました。
ここでは、3~4年前と最近1年
間の結果を図示し、NO2による大
気汚染の状況を比較します。(こ
れらの図は2009年11月1日(日)
に開催されたあつぎ環境フェアー
で展示したものです)
図1は3~4年前('05.12、
'06.6、'06.12)の結果、図2は最
近1年間('08.6、'08.12、'09.6)
の結果です。図1と図2とを比べ
るとNO2による大気汚染は明らか
に改善されたことが分かります。
3~4年前には環境基準を超え、
あるいは環境基準ゾーン内になる
ことがありましたが、最近1年間
には問題にならない濃度に低下し
ていることが分かります。日本で
発生するNO2は減少傾向にあると
|
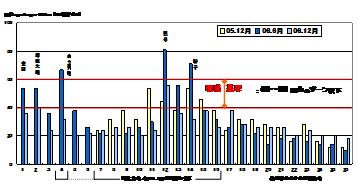
図1 3~4年前の厚木市内の二酸化窒素濃度
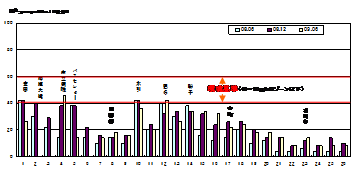
図2 最近1年間の厚木市内の二酸化窒素濃度 |